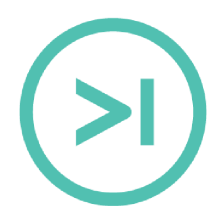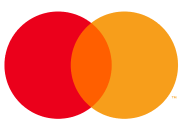今回のターンでウリキリます〜〜
ご入札をご検討いただき、誠にありがとうございます。
これは単なる宝飾品ではございません。一つの物語であり、哲学であり、これから人生の荒波に漕ぎ出す、すべての勇敢なる魂に捧げる護符(アミュレット)でございます。
長文となりますが、このジュエリーが宿す本当の価値をご理解いただくため、しばし私の拙い筆にお付き合いいただければ幸いです。
本文:
序章:窯焚きの翁
鎌倉の谷戸(やと)の奥深く、俗世の喧騒が蝉時雨に溶けて消える場所に、わしの庵(いおり)はある。北大路健山(きたおおじけんざん)。世間ではそう呼ばれておるが、本名はとうに忘れた。土を捏(こ)ね、火を焚き、器を焼く。ただそれだけの人生だ。人はわしを陶芸家と呼ぶ。美食家と呼ぶ者もおる。どちらも間違いではないが、正しくもない。わしはただ、本物を見極め、本物と共に生きることを信条とする、しがない老人(おいぼれ)に過ぎん。
わしの作る器は、決して安くはない。一見すれば歪(いびつ)で、釉薬(ゆうやく)の流れも気まぐれ。だが、分かる者には分かる。その歪さこそが、炎との対話の末に生まれた景色であり、作為を超えた美なのだ。わしの庵には、時折、その価値を解する客が訪れる。器を求め、あるいはわしが気まれに作る料理を求めて。
しかし、今日訪ねてきた若い男女は、少し毛色が違った。器でも料理でもない。彼らが求めていたのは、わしが道楽で集め、時として自ら手を加える「石ころ」……世間で言うところの、宝飾品であった。
玄関の土間で深々と頭を下げたのは、見るからに育ちの良さそうな青年と、その隣で控えめに微笑む、聡明そうな娘だった。
「北大路先生。突然のご訪問、お許しください。わたくし、佐伯健二と申します。こちらは、婚約者の美咲です」
「ふん。何の用だ。わしは陶芸家で、婚礼の仲人ではないぞ」
わしは轆轤(ろくろ)を回す手を止めずに、ぶっきらぼうに言った。土のひんやりとした感触が、指先から魂を吸い上げていく。この集中を妨げる者は、たとえ将軍様であろうと好かん。
「存じております。先生が、比類なき審美眼をお持ちであることも。実は私共、婚約の証となる品を探しておりまして。先生が秘蔵されているという、特別な首飾りを拝見したく……」
特別な首飾り、か。話が早い。わしの手元に、一本のネックレスがあることは、ごく一部の好事家しか知らんはずだが。どこで聞きつけたのか。
わしは手を洗い、二人を奥の座敷へと通した。そこは、わしの作品を並べた陳列室であり、客をもてなす食事の間でもある。窓の外には、手入れの行き届かない、ありのままの庭が広がっている。苔むした石、名も知らぬ野草、そして季節を告げる木々の葉擦れの音。
「まあ、座るがいい。だが、見せる前に、ちとわしの昔話に付き合ってもらおうか。腹も減っておろう。粗末なものだが、何かこしらえてやる」
わしはそう言うと、二人の返事も待たずに厨(くりや)へと向かった。あの首飾りを渡すに値する人間かどうか、見極めねばならん。わしの器がそうであるように、わしが認めた「本物」は、それを持つにふさわしい者の元へ行くべきなのだ。そして、人間性を見極めるのに、食事ほど雄弁なものはない。
第一章:相性という名の幻想
まず、土鍋で炊いたばかりの、つやつやと輝く白米を出した。米は魚沼の契約農家から、毎年わしが自ら足を運んで吟味したものだ。水は裏山の湧き水。これだけでご馳走だ。それに、自家製の糠漬けと、実山椒を効かせた昆布の佃煮を添える。
「さあ、食え。まずは腹の虫を落ち着けることだ」
二人は恐縮しながらも、小さな茶碗に盛られたご飯を口に運んだ。その瞬間、二人の目が驚きに見開かれるのを、わしは見逃さなかった。
「……美味しい。お米が、甘い……」
美咲と名乗った娘が、感嘆の息を漏らす。健二という青年も、何度も頷きながら、一心不乱に米を頬張っている。ふむ、悪くない。少なくとも、味覚が死んではおらんようだ。これが分からぬような輩(やから)に、わしの話をする価値はない。
「先生、このお漬物も……酸味と塩味の加減が絶妙です。きゅうりの歯ごたえが、まるで生きているようです」
「当たり前だ。命を頂いておるのだからな。きゅうりにも魂はある。その魂が喜ぶように漬けてやるのが、わしらの務めだ」
わしはどかりと二人の向かいに座り、燗(かん)をつけた酒をちびりとやった。
「して、お前さんたち。婚約、か。めでたいことだ。さぞ、相性が良いのだろうな」
わしの言葉に、二人は顔を見合わせて、幸せそうに微笑んだ。
「はい。自分でも驚くほど、価値観が合うんです」と健二。
「そうなの。食べ物の好みも、好きな映画も、笑いのツボも、ほとんど一緒で。一緒にいて、本当に楽なんです」と美咲。
来たか。これだ。現代の若者が口を揃えて言う、この「相性」というやつが、わしは何よりも気に食わん。
「ほう。楽、か。それは結構なことだ。喧嘩もしたことがないのではないか?」
「ええ、ほとんど。意見が食い違うことも、滅多にありませんし」
「ふん」と、わしは鼻を鳴らした。「愚か者どもめ」
ぴしり、と空気が凍った。二人は、わしが何を言ったのか理解できないという顔で、目を白黒させている。
「い、今、何と……?」
「愚か者、と言ったのだ。お前さんたちのような人間が、一番危うい。結婚というものを、まるで分かっておらん」
わしは猪口(ちょこ)に残った酒をくいと飲み干し、続けた。
「いいか、よく聞け。世の人間は、皆、勘違いしておる。結婚相手というのはな、自分と一番『相性の良い』人間と結ばれるべきではないのだ。むしろ逆だ。自分と最も『相性の悪い』人間と添い遂げるのが、道理なのだよ」
「そ、そんな……。滅茶苦茶です」
健二が、かろうじて反論の声を上げる。美咲は、ただただ困惑した表情でわしを見つめている。
「滅茶苦茶なのは、お前さんたちの頭の方だ。いいか、考えてもみろ。趣味が同じ、価値観が同じ、笑いのツボが同じ。そんな人間と一緒にいて、何が生まれようか。それは、ただの心地よい停滞だ。自分という存在の、安っぽい肯定に過ぎん。鏡を見て、自分は美しいと悦に入っているのと、何ら変わりはない。そこに成長はあるか? 発見はあるか? 魂のぶつかり合いから生まれる、新しい価値はあるか? ない。断じてない!」
わしは、厨から次の料理を運んできた。それは、早春に採れる蕗(ふき)の薹(とう)の天ぷらだ。揚げたてを、雪のような粗塩で食わせる。
「さ、食え。これも修行だ」
二人はおずおずと、その黒緑色の塊を口に入れた。途端、顔をしかめる。
「……苦い」
「そうだ。苦いだろう。春の苦みだ。雪の下で、冬の厳しさに耐え、ようやく顔を出した生命の味だ。この苦みがあるからこそ、後から追いかけてくる独特の香りが引き立つのだ。甘いだけの人生に、深みはない。料理も同じことよ」
わしは、自分の言いたいことの核心に、ゆっくりと近づいていった。
「お前さんたちが言う『相性』とは、要するに『楽』だということだ。自分を理解してくれる、肯定してくれる、波風を立てない相手。そんなものは、友人か、ペットで十分だ。配偶者というものは、そうであってはならん」
「では、どうあるべきだと?」
美咲が、真剣な眼差しで問いかけてきた。見込みがあるかもしれん。
「配偶者とはな、自分の理解の範疇を、ことごとく超えてくる存在でなければならんのだ。『なぜ、この人はこんなことを言うのか』『なぜ、こんな行動を取るのか』。全く理解できない。腹が立つ。時には憎しみさえ覚える。だが、その『分からなさ』と向き合うことこそが、結婚の本質であり、人生そのものなのだ」
「それは……ただの苦行ではありませんか?」
健二が、納得のいかない顔で言う。
「その通り! これこそが『修行』なのだよ。我々が、この世に生を受けてきた意味は、楽をするためでも、幸せになるためでもない。魂を磨き、成長するために生まれてきたのだ。そして、魂を磨くのに、砥石(といし)が必要だろうが。自分と同じ、ふにゃふにゃの粘土同士をこすり合わせたところで、何も変わりはせん。自分とは全く組成の違う、硬く、ざらついた、理解しがたい砥石。それこそが、伴侶なのだ。その砥石と、毎日毎日、四六時中、体をこすりつけ、火花を散らし、時には身を削られ、痛みに耐える。その果てに、ようやく己の角が取れ、丸みを帯び、内なる輝きが滲み出てくる。これが、人間が成熟するということの、唯一の道筋なのだよ」
わしは熱っぽく語りながら、二人の顔色を窺った。健二はまだ不満げだが、美咲の瞳には、先ほどの困惑とは違う、思索の色が浮かんでいた。
第二章:器と歴史が語るもの
「まあ、そんな難しい話は、腹が減っていては分からんか。次だ、次」
わしは、今度は椀物を出した。わしが昨年の秋に焼いた、黒織部(くろおりべ)の椀だ。わざと歪ませた沓形(くつがた)で、黒釉の上に、鉄絵で無造作な文様が描かれている。見る者によっては、ただの失敗作にしか見えんだろう。
蓋を開けると、ふわりと湯気と共に、極上の鰹出汁の香りが立ち上った。中には、葛(くず)を打った甘鯛(あまだい)、それに寄り添うように、焼き目のついた椎茸と、一筋の柚子。
「この椀を見ろ」と、わしは言った。
「これは、織部焼だ。安土桃山時代、茶人であり武将でもあった古田織部(ふるたおりべ)が指導して作らせた、破格の焼き物よ。それまでの茶碗といえば、唐物(からもの)や高麗(こうらい)の、端正で静謐な美が尊ばれてきた。そこへ、織部はどうだ。わざと器を歪ませ、緑の釉薬をまだらに掛け、稚拙な絵を描き込んだ。当時の価値観からすれば、まさに『相性の悪い』、異端のデザインだ。だが、この歪さ、この破調こそが、それまでの美意識を打ち破り、新しい日本の美を創造したのだ。もし織部が、既存の価値観と『相性の良い』、無難なものばかり作っていたら、どうなっていたか。ただの模倣で終わり、歴史に名も残らなかっただろう」
二人は、椀の中身を味わいながら、黙ってわしの話を聞いている。
「人間関係も、これと同じことだ。自分という器に、相手という、これまで見たこともないような、理解しがない釉薬が掛かる。熱い窯……つまり、日々の生活という名の試練の中で、両者は反発し、溶け合い、時にはひび割れさえ起こす。だが、その窯から出てきた時、予想だにしなかった美しい『景色』が生まれていることがある。それこそが、夫婦という合作の、唯一無二の価値なのだ」
「でも、先生。完全に価値観が違う相手とでは、生活が成り立たないのでは? 離婚してしまうケースの方が多いように思います」
健二が、もっともな疑問を口にした。
「うむ。そこが肝心なところだ。だからこそ、最初に『覚悟』がいるのだよ。この理解不能な相手と共に、己を磨き上げるのだという、揺るぎない覚悟がな。その覚悟さえあれば、どんな困難も、魂の成長の糧となる。だが、初めから『楽』や『心地よさ』を求めているから、少しの不都合で『相性が悪い』と投げ出してしまうのだ。まったく、本末転倒も甚だしい」
わしは、おもむろに立ち上がると、蔵の中から桐の箱を一つ、恭しく運んできた。ずしりと重い。その箱を、二人の前に静かに置いた。
「お前さんたちが、見たいと言っていた品だ。だが、その前に、この品が持つ歴史と、わしとの因縁について、話さねばならん」
桐箱の蓋を開ける。中には、紫色の袱紗(ふくさ)に包まれた、一本のネックレスが鎮座していた。
第三章:一カラットのダイヤモンドに宿る、星の圧力
「これは、ただのダイヤモンドの首飾りではない。わしの、魂の一部だ」
わしは、ゆっくりと話し始めた。
「わしの師は、魯山人(ろさんじん)……と、世間では呼ばれていたが、わしにとってはただの頑固で、気難しく、そして誰よりも本質を見抜く力を持った大先生だった。先生は、食と器は一体であるという『器は料理の着物』という思想を掲げ、自ら土を捏ね、料理をこしらえた。わしはその背中を見て、全てを学んだ。美とは何か。本物とは何か。生きるとは、どういうことか」
「ある時、先生が、どこからか一つの石を手に入れてきた。磨かれる前の、ダイヤモンドの原石だ。それは、ただの鈍い光を放つ石ころにしか見えなかった。先生は、それを手のひらで転がしながら、こう言った。『健山、これが見えるか。これはな、ただの炭素の塊だ。地球の奥深く、マントルの中で、想像を絶するほどの圧力と熱に、何億年もの間耐え抜いた末に、この姿になったのだ。楽な環境では、ダイヤモンドは生まれん。炭は炭のままだ。人間も同じだ。安楽な場所にいては、魂は磨かれん』と」
「先生は、その石を最高の職人に託して、磨き上げさせた。そして、出来上がったのが、この一粒のダイヤモンドだ。1.030カラット。寸分の狂いもない、見事なラウンド・ブリリアントカット。光を取り込み、その内部で全反射を繰り返し、虹色の輝き……ファイアとなって放つ。これこそが、苦難の果てに得られる、魂の輝きそのものだと、先生は言った」
わしは、ネックレスを袱紗から取り出し、テーブルの上に置いた。
しん、と静まり返った部屋の中で、その一粒のダイヤモンドは、窓から差し込む僅かな光を全て集め、自らが光源であるかのように、圧倒的な存在感を放っていた。
「見ろ。この石を支える台座。これはPt900。純度90パーセントのプラチナだ。プラチナという金属は、非常に重く、安定しており、王水以外では溶かすことができん、不変の象徴だ。熱にも酸にも強く、決して錆びることも、変色することもない。なぜ、ダイヤモンドを支えるのが、このプラチナなのか。それは、この台座が『覚悟』を象徴しているからだ」
わしは、ペンダントの裏側を二人に見せた。そこには、くっきりと「Pt900」そして「1.030」という刻印が打たれている。
「この刻印は、ただの品質表示ではない。これは『誓い』だ。この1.030カラットの、計り知れない圧力と歴史を宿した魂(ダイヤモンド)を、わしは決して変質することのない、揺るぎない覚悟(プラチナ)で支え続ける、という誓いの証なのだ。この台座のデザインを見ろ。六本の爪で、がっしりと石を掴んでいる。華美な装飾はない。ただ、ひたすらに、このダイヤモンドという『試練』であり『輝き』である存在を、正面から受け止め、支え、その美しさを最大限に引き出すためだけの、実直なデザインだ。これこそが、夫婦の在るべき姿ではないのか?」
二人は、息を呑んで、その小さな宇宙を見つめている。
「そして、この鎖。これはPt850。台座より少しだけ純度を落とした、しなやかなプラチナだ。ベネチアンチェーンという、四角い箱を繋いだような、これもまた実直で、切れにくい構造をしておる。これは、日々の生活そのものを表している。決して切れることのない、信頼と継続の鎖だ。そして、これを見ろ」
わしは、留め金の近くにある、小さな球を指さした。
「これは、スライドアジャスターという機構だ。この球を動かすことで、最大45センチまで、自由に長さを変えることができる。ガチガチの覚悟だけでは、息が詰まる。時には、状況に応じて、関係性の距離感を調整する『しなやかさ』も必要なのだ。厳格な規律の中に、僅かな遊びと柔軟性がある。これもまた、長く続く関係の極意だ」
健二が、ようやく口を開いた。
「先生……。このネックレスは、ただの宝飾品ではないのですね。先生の、そして、そのお師匠様の、人生哲学そのものが、ここに凝縮されている……」
「その通りだ」と、わしは頷いた。「わしは、師が亡くなられた後、このネックレスを譲り受けた。そして、これを身に着けるにふさわしい人間が現れるのを、ずっと待っていた。ただ金があるだけの成金や、ブランドの名前でしか価値を判断できんような輩には、決して渡すつもりはなかった。この石が持つ『圧力の歴史』と、プラチナが象徴する『不変の覚悟』、そして、この首飾り全体が語りかける『相性の悪さこそが成長の糧である』という、厳しい真理。それを理解し、受け入れる覚悟のある者にしか、この『金剛不壊(こんごうふえ)』の輝きを託すことはできん」
金剛不壊。仏教の言葉で、ダイヤモンドのように硬く、決して壊れることのないもののことだ。わしは、このネックレスをそう呼んでいた。
第四章:本当の伴侶
美咲が、震える声で言った。
「先生……。私、恥ずかしいです。今まで、健二さんとの関係を『楽だから』『価値観が合うから』という理由で、素晴らしいものだと思い込んでいました。でも、それはただ、自分と向き合うことから逃げていただけなのかもしれません。私たちは、お互いにとって、心地よい鏡でしかなかったのかもしれません……」
彼女は、健二の顔をじっと見つめた。その瞳には、涙が浮かんでいた。
「健二さん。私とあなたは、本当に相性が良いのでしょうか。いいえ、きっと、そうではないはずです。私が知らない、あなたの嫌なところ。あなたが見ていない、私の醜いところ。これから、たくさん出てくるはずです。私たちは、まだお互いの表面しか見ていない。これから先、きっと、先生がおっしゃるように、理解できなくて、腹が立って、憎らしく思うことさえあるのかもしれない。その時、私たちは……」
健二は、黙って美咲の話を聞いていたが、やがて、彼女の手を強く握りしめた。
「美咲……。僕も、同じことを考えていた。先生の話を聞いて、目が覚めるような思いだった。僕たちは、結婚をゴールだと思っていた。でも、違うんだ。結婚は、スタートなんだ。それも、平坦な道のりじゃない。お互いを砥石にして、魂を磨き上げていく、長く険しい修行の道のりの、始まりなんだ」
彼は、わしの方を向き、深く、深く頭を下げた。
「先生。僕たちに、この首飾りをお譲りいただけないでしょうか。これは、僕たちの『完璧な愛の証』ではありません。僕たちが、これから始まるであろう、困難に満ちた『修行』に、共に立ち向かうという『覚悟の証』として、身に着けたいのです。このダイヤモンドが、何億年もの圧力に耐えてきたように。このプラチナが、決して変質しないように。僕たちも、お互いという『最も相性の悪い』最高のパートナーと共に、生涯を掛けて、自分たちだけの輝きを、磨き上げていきたいのです」
その言葉に、嘘はなかった。青年の顔は、先ほどまでの甘さを脱ぎ捨て、厳しい覚悟を決めた男のそれに変わっていた。美咲もまた、涙を拭い、凛とした表情で頷いている。
ふん。面白い。
まさか、わしの捻くれた説法を、ここまで真っ直ぐに受け止める若者がいようとは。
わしは、しばし黙って二人を見つめた後、ゆっくりと口を開いた。
「よかろう。その覚悟、本物と見た。この『金剛不壊』は、お前さんたちに託そう。だが、勘違いするな。これは、贈り物ではない。お前さんたちが、これから背負っていく『十字架』であり『道標』だ。その重さを、その輝きを、片時も忘れるな」
わしはネックレスを手に取り、美咲の首に、そっと掛けてやった。
ひんやりとしたプラチナの鎖が、彼女の肌に触れる。そして、胸元で、1.030カラットのダイヤモンドが、まるで命を得たかのように、眩いばかりの光を放ち始めた。それは、ただ美しいだけではない。厳しい覚悟と、計り知れないほどの時間の重みを内包した、尊厳のある輝きだった。9.25ミリという、決して小さくはないその一粒は、彼女の華奢な鎖骨の下で、圧倒的な存在感を主張していた。総重量2.06グラム。物理的な重さ以上の、魂の重みが、そこにはあった。
「……ありがとうございます」
美咲は、胸元の輝きに手を触れ、もう一度、深く頭を下げた。彼女の頬を伝う涙は、もはや悲しみや困惑の色ではなく、決意と感謝に濡れていた。
終章:一期一会
二人が帰った後、庵には、またいつもの静寂が戻ってきた。
わしは、残った料理を肴に、一人で酒を飲む。
あの若者たちは、これからどうなるだろうか。
わしの言った通り、きっと壮絶な喧嘩もするだろう。お互いの理解不能な部分に、何度も絶望するに違いない。価値観の違いに、心が引き裂かれるような思いもするだろう。
だが、それでいいのだ。それがいいのだ。
その度に、美咲の胸元で輝くあのダイヤモンドを見るがいい。
地球の圧力に耐え抜いた、炭素の結晶を。
決して揺るがぬ覚悟を象徴する、プラチナの台座を。
そして、思い出すがいい。今日この日、このわしの庵で、何を誓ったのかを。
相性の悪さこそが、最高の砥石。
困難こそが、魂の成長の糧。
結婚とは、安住の地ではない。互いの魂を鍛え上げる、終生の道場なのだ。
わしは、空になった徳利を手に取り、厨へと向かう。
また、新しい土を捏ねねばならん。
窯に火を入れ、まだ見ぬ器を焼かねねばならん。
わし自身の修行も、まだ道半ばだ。
あの若い二人に、偉そうなことを言えるほどの人間ではない。
だが、確信していることがある。
本物とは、厳しいのだ。
美とは、痛みを伴うのだ。
そして、本当の愛とは、心地よさの中にはなく、共に困難を乗り越える覚悟の中にこそ、宿るのだということを。
谷戸の奥に、夜の帳が下りてくる。
わしの庵の窓に、ぽつりと灯りがともった。
それは、まるで遠い星の輝きのようでもあり、また、誰かの胸元で静かに輝き続ける、あのダイヤモンドの光のようでもあった。
人生という、一期一会の、長くて短い修行の道を、照らす光。
わしは、もう一杯だけ燗をつけると、満足げに目を閉じた。
悪くない一日だった。



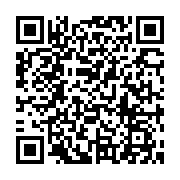

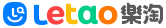
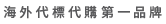












 好評 (74,153)
好評 (74,153)
 差評 (23)
差評 (23)