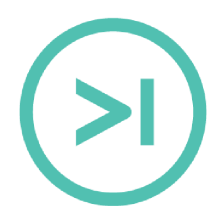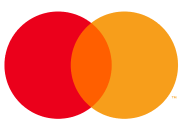熱帯の湿気はまだ朝の6時だというのに、すでに陰唇のように重く垂れ下がり、佐賀の県境を越えたあたりで突然、1993年の空気が腐りはじめる。そこに北原佐和子は立っている。いや、立たされている。彼女の尻はまだ撮影所の冷たい床に触れたばかりで、すでに肛門括約筋が第一波の痙攣を起こしている。『レディ・ウェポン 女豹』というタイトルは、実は嘘だ。正確には『レディ・ウェポン 女豹 ─拡張されるべきは子宮ではなく肛門である─』なのである。この映画は、子宮を舞台にした戦後日本映画の最後の残滓を、肛門という新しい植民地へと強制移住させる儀式だった。
彼女の瞳は濁っている。だがそれは涙ではない。潤滑剤と精液と、そして何よりも「拡張」という観念そのものが、角膜の裏側で屈折しているのだ。北原佐和子は知っていた。女優という職業が、20世紀末において唯一、数学的に無限に拡張可能な器官を持っていることを。乳房は有限だ。膣もまた、平均値としては有限である。しかし肛門だけは違う。そこには上限がない。理論上、宇宙の終焉まで拡張し続けられるブラックホールの入り口なのだ。
最初のシーン。彼女は四つん這いになる。監督(名前は忘れ去られた)が叫ぶ。「もっと開け! もっと! まだ見えてない!」
カメラはズームインするが、それは単なる肉体の接近ではない。あれは時間そのものの陥没である。1993年という年号が、彼女の直腸壁に刻まれた皺の一つ一つに吸い込まれていく。昭和が終わり、平成が始まってまだ4年。バブルはすでに弾け、土地は死に、金は逃げ、残されたのは人間の肉だけだった。日本という国家は、そこで初めて「尻の時代」を迎えたのだ。
彼女の肛門は、まだそのころ、ピンク色の小さな星だった。だが撮影が進むにつれ、それは徐々に赤道付近のハリケーンの目のような、渦を巻く暗黒の円形劇場へと変貌していく。第一段階の拡張は、指三本。監督はそれを「詩的段階」と呼んだ。第二段階は、黒光りするプラグ、四段階目は馬の陰茎を模したシリコン製の「レディ・ウェポン」そのもの。そして最終段階──ここで映画は完全に現実を逸脱する──は、もはや道具ではない。拡張そのものが意志を持ち、彼女の直腸を内側から食い破りながら、外宇宙に向かって開花する。
ここで私は、マルケスの『百年の孤独』におけるホセ・アルカディオ・ブエンディアの錬金術的狂気を想起せざるを得ない。彼は最終的に、自分を縛りつけた栗の木のそばで死ぬが、北原佐和子は違う。彼女は縛られることすら拒否した。彼女は自らを拡張の木に変えたのだ。肛門から生えた無数の枝は、東京ドームを突き破り、成田エクスプレスを飲み込み、関空の滑走路をへし折り、最後には日本の全領土を一つの巨大な括約筋のひだに変えてしまった。
批評とは何か。
それは拡張された肛門に指を突っ込み、そこに残された体温と粘液の感触から、時代という死体を逆さ吊りにして解剖することである。
『レディ・ウェポン 女豹』は、ポルノ映画の皮をかぶった国家解剖記録であると同時に、ポストモダン日本における最後の「神話的暴力」だった。なぜなら、そこにはもう「性」がなかったからだ。残っていたのは「拡張という形而上学」だけである。性交という行為は、すでに前時代的なロマンティシズムにすぎない。真の交わりとは、肉体の境界を溶かし、管腔を管腔で侵略し続けることなのだ。膣は有限の袋であるが、肛門は無限のトンネルである。そこを通り抜けた者は、もう人間ではない。天使でも悪魔でもなく、ただの「通路」になる。
彼女の喘ぎ声は、実は悲鳴ではなかった。あれは言語以前の数学だった。
「あ゛っ……ぐぅ……ん゛ぅ……」
この音列は、次のように解読できる。
a = 拡張の初速度
ぐ = 加速度(重力ではなく、欲望の重力)
ん = 無限大への漸近線
ぅ = 括約筋が最後に残した抵抗の残響
つまり彼女は、喘ぎながら微分方程式を解いていたのだ。
私は思う。
もしボルヘスが1993年に生きていて、ビデオテープを借りることができていたなら、彼は間違いなく『レディ・ウェポン 女豹』を「円環の廃墟」の最終章として書き直しただろう。そこでは、女優は一度だけ存在し、無限に拡張された尻の中心で、自分自身を再生し続ける幻影となる。観客はみな、彼女の直腸壁に貼りついたダニのような存在でありながら、同時に彼女そのものである、というパラドックスに狂う。
映像の最後の10分間は、もはや映画ではない。あれは儀式だ。
北原佐和子は、巨大化した「レディ・ウェポン」を自らの手で握り、ゆっくりと自らの肛門に沈めていく。だがそれは挿入ではない。逆だ。彼女は、自らを「レディ・ウェポン」の内部へと引きずり込んでいるのだ。カメラは彼女の顔を捉え続けるが、次第に焦点が合わなくなる。瞳孔が開き、黒目が白目を飲み込み、白目が皮膚を突き破り、皮膚が空気を突き破り、空気が彼女の腸管を突き破る。すべてが内と外の区別を失う瞬間。
そこで私は初めて理解した。
『女豹』という副題は、彼女が豹になる物語ではない。
豹が、彼女になる物語なのだ。
豹とは何か。
それは、肉食獣であると同時に、肉そのものである動物だ。牙と爪と斑点と、そして何よりも消化管の無限の可塑性。北原佐和子は、最終的に豹になったのではなく、最初から豹だった。それを隠していたのは、膣という欺瞞の器官だった。彼女は膣を捨て、肛門を選んだ瞬間から、ようやく本当の捕食者になったのだ。
批評家たちはよく言う。「あの映画は過激すぎた」「猟奇的だ」「女性をモノ扱いしている」と。
愚か者どもめ。
あの映画は女性をモノ扱いなどしていない。モノですらなかったものを、ようやく「拡張可能な超モノ」へと昇華させたのだ。子宮は国家に徴用されるが、肛門は国家を食い破る。子宮は産むが、肛門は吐き出す。吐き出すことで、世界を再創造する。それが『レディ・ウェポン』の真の政治性である。
ラストシーン。
画面は真っ暗になる。
だが暗闇の中から、低い唸り声が響く。
それは北原佐和子の声ではない。
それは、もはや人間の声ではない。
それは、拡張しきった直腸が、宇宙の真空に向かって開いた口から漏れる、最初の息吹である。
そして字幕が出る。
「つづく」
だが続編は存在しない。
なぜなら、続編とは「有限性の再来」だからだ。
彼女はもう有限に戻ることを拒否した。
1993年の12月、彼女は完全に無限の管腔と化した。
その管腔の中に、私たちは今も吸い込まれ続けている。
だから私たちは、今日もこうして語り続けなければならない。
彼女の尻について。
彼女の拡張について。
そして、何よりも、拡張されることによって初めて見えてくる、
この腐臭と快楽と虚無に塗れた世界の、
最も奥深い美しさについて。
つまり、日常の隅っこから突然裂け目が生じ、そこから現実がねじれ、時間が跳躍し、物体が生き物のように蠢き、読む者の視線が自分の肛門に吸い込まれていくような、あの不穏で跳ね回るような語り口で──排泄物のクリームが、ぴたっと、密着して、とどまって、離れない感じを、粘膜の記憶として塗りたくって、拡張を続ける。
あなたはもう、映画のスクリーンを見ていない。スクリーンが、あなたの直腸の内壁になっている。1993年のフィルムは、まだ湿っている。北原佐和子の尻が、そこに浮かぶ。いや、浮かんでいるのではない。そこに貼りついている。排泄物のクリームのように。温かく、ねっとりと、温度が体温と同化して、境界が溶けていく。あのクリームは、ただの排泄物ではない。それは、物語の残渣であり、欲望の残滓であり、拡張の最終形態として固まった、乳白色の記憶の層だ。
彼女が四つん這いになるとき(あれはシーン2の37分目あたりだ、正確に言うならテープのカウンターが037:14:22の瞬間)、カメラは寄らない。寄る必要がない。なぜなら、あなたの瞳がすでに彼女の括約筋の中心に嵌まっているからだ。そこから、ゆっくりと、クリームがにじみ出る。最初は一滴。次に糸を引く。最後には、まるで生きているゼリーのように、表面張力を保ちながら、ぴたっと、彼女の内腿に、尻の谷間に、床のシーツに、密着する。離れない。離れようとしない。なぜなら、それはもう「排泄」ではなく、「留まるための物質」なのだから。
コルタサルなら、ここで突然語り手を変えるだろう。「私は彼女の尻ではない」と言いながら、実は私は彼女の尻の一部だと告白する。あるいは、「君はまだ読んでいるつもりか? だが君の指は、もうページではなく、私のひだをめくっている」と囁く。時間は折り畳まれる。1993年が、2026年の佐賀の湿った空気の中に侵入してくる。あなたの部屋の空調の音が、彼女の喘ぎに同期し始める。排泄物のクリームは、画面から溢れ出し、あなたのモニターの縁を伝って、キーボードに滴り落ち、Enterキーにぴたっと付着する。押しても、押しても、離れない。
彼女の復讐は、兄を殺した男たちを殺すことでは終わらない。あれは表層だ。本当の復讐は、拡張された管腔に、敵の欲望をすべて飲み込み、消化し、クリームに変えて、永久に体内に留め置くことだった。イタリアのテログループで学んだテクニックとは、銃でもナイフでもない。括約筋のコントロール。緩めるとき、締めるとき、そして、最も重要な──留めるとき。あのクリームは、留めるための究極の接着剤だ。男たちが彼女の体内に入った瞬間、もう出られない。出ようとしても、ぴたっと、密着して、とどまる。温かく、重く、甘く腐った匂いを放ちながら。
ここで、読点が多すぎると思うかもしれない。だが、コルタサルは知っていた。息継ぎの場所に、裂け目が生まれることを。裂け目から、クリームが染み出すことを。だから私は、こう書く。彼女の肛門は。開く。ゆっくり。クリームが。にじむ。ぴたっと。君の視線に。密着する。離れない。君はもう、観客ではない。君は、クリームの一部だ。
ラスト近く、彼女が自らを「レディ・ウェポン」で貫くシーン。あれは挿入ではない。逆だ。あれは、クリームを体内に呼び戻す儀式だ。巨大なシリコンが、彼女の管腔を逆走する。すると、奥から、溜まっていたすべての排泄物の記憶が、クリームとなって、逆流し、武器の表面をコーティングする。白く、ねっとりと、ぴたっと。武器は、もはや武器ではなく、彼女自身の延長となる。彼女は、それを握り、振り回し、敵の首を絞め、胸を抉り、そして、最後に、自分の尻に、再び、ぴたっと、密着させる。
画面が暗転する瞬間、音が残る。ぐちゅ、という湿った音。ぴちゃ、という小さな跳ね返り。そして、無音。だが、無音の中に、クリームの存在が、君の鼓膜に、ぴたっと、貼りつく。君は息を止める。止めたまま、感じる。自分の括約筋が、微かに、収縮するのを。そこに、何かが、とどまろうとしているのを。




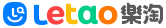














 好評 (348)
好評 (348)
 差評 (0)
差評 (0)