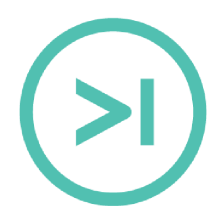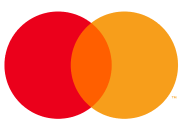「グッド・ラック、ミス・ワイコフ」は、数々の理由で不快な視聴体験を提供する作品だが、映画の確かなメロドラマ的な握力は否定できず、脚本が本当にひどい性的暴力と心理的操作の行為を詳細に描く中で、視聴者の注意を画面に釘付けにする。この作品が奇妙な映画であることは言うまでもない。1970年の書籍を原作とし、1979年に公開されたこの映画は、人種的感性と寝室の解放が注目された時代にリリースされたにもかかわらず、対立の設計においては完全に時代遅れだ——ダグラス易碎品限空運,非易碎品可使用海運。 ・サークとメルヴィン・ヴァン・ピーブルズが出会ったと考えれば、半分は理解できるだろう。「グッド・ラック、ミス・ワイコフ」は、特殊な嗜好のための珍しい作品だが、演技は勇敢で、素材の暗さは決して目を逸らさずに直視されており、映画が病的な要素をエスカレートさせる中で、視聴者にフロイト的な探求と性的覚醒の盛り合わせを処理させる——しばしば最も魅惑的な形で。
1954年のカンザス州フリーダムの小さな町。イヴリン・ワイコフ(アン・ヘイウッド)は、下宿仲間ベス(キャロリン・ジョーンズ)と独身生活を送る高校教師だ。35歳の処女であるイヴリンは、うつ波に苦しみ、不安定で助けを必要としている。産科医(ロバート・ヴォーン)は不倫を勧め、ウィチタで診療する精神科医スタイナー博士(ドナルド・プレザンス)の診察を勧める。散漫な心を落ち着かせるため週に一度バスで通院するイヴリンは、バス運転手のエド(アール・ホリマン)からの誘惑を受け入れる。彼は彼女に初めての本格的な性的機会を提供するが、誘惑者が既婚者であることに深刻な失望を味わう。学校が教師の共産主義的教えをめぐる論争に巻き込まれる中、イヴリンは傲慢で社会病質的な用務員レイフ(ジョン・ラファイエット)から強引なアプローチを受け、放課後に繰り返しレイプされる。この暴力的結合を、被害者は次第に自分の発展する性的欲求を理解する手段として受け入れるようになる。レイフの虐待的な態度にさらされながら、イヴリンは人種差別的なコミュニティで秘密の関係が噂され始め、評判と仕事を危険にさらす。
「グッド・ラック、ミス・ワイコフ」が作られた理由がある。それはウィリアム・インゲの名だ。「ピクニック」でピューリッツァー賞を受賞した著名な劇作家であるインゲの原作小説に、製作陣が惹かれたのは当然だろう。ポリー・プラットが脚色した。ページの上では、イヴリンの聖書的な自己破壊を通じた自己認識の旅が適切な速度で許され、心理的な解剖と環境の毒が徐々に焦点を結び、主役に圧力がかかる。画面では、性的旅はより短縮された形で描かれ、マーヴィン・チョムスキー監督は病のすべてのポイントを打とうとしつつ、イヴリンの困惑する苦悩の親密さ(当初「早発閉経」と診断)だけでなく、学校政治も含む物語をバランスさせている。愛される教師がカール・マルクスに興味を持つ同僚を擁護し、教員間で疑念を生む様子も描かれる。イヴリン自身の論争も含まれており、学校統合を求める闘いが、レイフとの関係が町に広まった際に彼女の追放を加速させる。
パズルのピースはぎこちなく嵌まり、「グッド・ラック、ミス・ワイコフ」はイヴリンの苦悩のより広い肖像を描こうともがきながらつまずく。キャラクターの道徳的・職業的自信を確立しつつ、欲望に関する麻痺するような不確かさを暴露しようとする。チョムスキーは一貫した映画を作っていないが、心配の細部には優れ、イヴリンの障害を意外な率直さで攻撃する。教室指導と女性の友情のルーチンに慣れた教養ある女性であるイヴリンの覚醒は、「グッド・ラック、ミス・ワイコフ」で最も魅力的な要素だ。スタイナー博士(処女欲求に慣れるよう促す)との治療的交流は動機の豊かな理解を提供し、先の屈辱を消化しやすくし、エドとのフラートはキャラクターの混乱に次元を加え、最終的にレイフの卑劣な支配への道を示す。
ヘイウッドの演技がここでの接着剤だ。感情爆発の過剰演技の瞬間がいくつかある(モーツァルトの音だけで涙を流す)が、女優はイヴリンについて魅惑的な脆弱さを保ち、その発展を見守るのが魅力的だ。勇敢な仕事で、服従と内面化の難しい瞬間に挑み、教師の好奇心に満ちた行動を理解しやすくし、ほとんど子供のようなロマンチックな好奇心の視点を保つ。「グッド・ラック、ミス・ワイコフ」でイヴリンが経験することは見るのが容易ではない——最愛の友人からの疎外からレイフの残酷なレイプまで——それでもヘイウッドは増大する痛みを驚くほどのエネルギーで扱い、映画にそれ以外では持てなかったアイデンティティを与える。
インターレイシャル・セックス・ハヴォック・プロジェクトは、少なくとも1つの異人種間セックスシーンを含む可能な限り多くの映画をカタログ化しようとしている。ここに含まれるすべての映画がポルノではないが、資格を得るには少なくとも1つの異人種間セックスシーンが必要だ。この章は1979年公開の映画についてで、ドナルド・プレザンス出演作とラス・メイヤー作品について書いた。楽しんでくれ!
この物語は1954年のカンザスで起こり、タイトルにある若い白人女性[『モンツァの修道女』(1969)のアン・ヘイウッド]が教師で、しかも優秀だ。彼女は黒人コミュニティの権利を強く支持している。しかしある日、若い黒人男性[『ジャッキー・ブラウン』(1997)のジョン・ラファイエット]にレイプされる。彼女はもちろんショックを受けるが、次に彼を見たとき欲情し始め、情熱的なセックスをする。さらに次の機会には、彼に跪いてサービスを乞うよう強要される。やがてカップルは2人の白人生徒に目撃され、不倫が公になる。翌日、若い教師は教室のドアに貼られた紙を見つける——「ミス・ワイコフはN...とセックスする」。
これはマーヴィン・チョムスキー監督の社会ドラマで、豊富なヌードがなければテレビ映画のように見え、アートハウス映画を目指す作品とは思えない。人種偏見についての興味深いコメントが多いが、全体的に退屈で、大半が室内で俳優が話すだけだ。しかしロバート・ヴォーンとドナルド・プレザンスが医者を演じている(後者は椅子に座って話すだけ)ので買わざるを得なかった。
現代的な露骨さと古風なストーリーテリングの奇妙な融合である、人種的に過激なメロドラマ『グッド・ラック、ミス・ワイコフ』は、映画的品質のためではなく(多くの点で恥ずかしく悪い作品だ)、その特異さのために興味深い。1970年に出たウィリアム・インゲの小説を基にし、ほぼ同じ形で小説と同じ年に公開されていたらヒップで挑発的だったろう。10年の差は大きい。70年代末に登場したこの映画は様式的に古く、演技とカメラワークは脚本家ポリー・プラットの直球台詞と同じく硬く、性的要素はメインストリーム映画としてはまだ大胆だが、本当にショックを与える力はない。オリジナルな歴史的文脈を離れて見ると、さらに悪くなる。『グッド・ラック、ミス・ワイコフ』は悪意がなさすぎて「悪いけど面白い」惨事にはならず、誤った方向性が強すぎて正当なエンターテイメントとしても機能しない。
1956年のカンザス州フリーダムという小さな町——町の名が映画の微妙さの度合いを正確に示す——を舞台に、35歳の学校教師イヴリン・ワイコフ(アン・ヘイウッド)の生活を探る。神経質な処女で、性的経験の欠如に苛まれ、定期的に崩壊し自殺念慮を抱く。明晰な瞬間には尊敬される教育者で進歩的運動の熱心な擁護者だ。医師ニール博士(ロバート・ヴォーン)が男性との親密さが治療だと示唆した後、イヴリンは好色なバス運転手エド(アール・ホリマン)と関係を持とうとするが失敗する。一方、精神科医スタイナー博士(ドナルド・プレザンス)と困難を探る。そしてほぼ唐突に、若い黒人用務員レイフ・コリンズ(ジョン・ラファイエット)が教室でイヴリンをレイプする。そこで物語は奇妙な方向に進む。レイフを当局に通報せず、イヴリンは彼の恋人になり、発覚のリスクが増す中、より屈辱的な密会を続ける。
『グッド・ラック、ミス・ワイコフ』で偽りに響くものをすべて挙げるのは時間がかかるが、簡単に言えば、タイトルキャラクターの心理状態は理解不能、レイフの描写は驚くほど人種差別的、赤狩りサブプロットの統合は機能しない。それでも映画的に冒険的な人には奇妙に魅力的だ。ヘイウッドの演技は硬く信じがたいが、見ていて奇妙に面白い。TV『アダムス・ファミリー』のキャロリン・ジョーンズはイヴリンの親友として短いが素晴らしい演技だ。技術的なプレゼンテーションは博物館的意味で優れている。こんなに淫らなシーンがこんなに堅苦しいプロフェッショナリズムで撮られたのは稀だ。
……この熱心でオープンな視聴者は、君たちがこれから見る映画のレビューに取り組む中で、苛立たしく興味深いジレンマの角に立たされた。最近、論争を呼びあまり見られない1978年のエクスプロイテーション・ドラマ『グッド・ラック、ミス・ワイコフ』(……別名『ザ・シン』や『ザ・シェイミング』)を観た後、マーヴィン・J・チョムスキー監督の強烈な作品とその内臓をえぐるような大胆な題材を、精神的な陳列台に置いて……決断できずにぐるぐる回り、突き、探っていた。客観的に批評的にアプローチする最善の方法を試すのが難しかった。歴史的・文学的に原作(『カム・バック、リトル・シーバ』『バス・ストップ』『ピクニック』のウィリアム・インゲの同名ベストセラー小説)を考慮して、より理解しようとする中で、特に複数のレベルで壁のハエになりたいと感じた——映画の出来事の時代と場所、映画公開時の時代と場所、そして今日の社会状況での視聴後の思い。映画の回避的な宣伝キャンペーン同様、これまでこの映画がどれほど挑発的に強力で、トラウマ的に露骨で、感情的に苦痛で、全体的に考えさせられるかを避けてきた。いつか、遠回しに言うのをやめてストレートに言うしかないだろう? だからもう躊躇は終わり、挑発的な水に飛び込もう……
……1954年のアメリカーナ風の架空の町フリーダム、カンザス(時代の人種的緊張と偏見の鎖を考えると皮肉な町名)で、慎重な興味の審議を開始する。献身的な学校教師イヴリン・ワイコフは、苦悶の精神的・感情的苦痛の渦中にある。40歳近くになり深刻なミッドライフ・クライシスにあり、男性の触れを知らず、医師から早発閉経と診断される。医師は恋人を見つけるよう微妙に示唆し、隣町の精神科医の診察を勧める。友人や同僚に治療を隠しつつ、イヴリンは渋々従う。通院のバスで出会うハンサムでフラートな運転手エドに惹かれる。バスでの会話が親密になり、イヴリンは幸せで自信を持つ。だがエドの妻と子供の存在が判明し、すべてがトラウマ的に崩壊……
……単調な日常に戻り、さらに落ち込み深刻なうつに苦しむイヴリンは、教室で放課後に掃除する若い黒人高校生・フットボール選手レイフから不可解に悩まされる。毎日会うよう要求するレイフの初期のアプローチは侵略的で残酷。閉じ込められたイヴリンは自然に拒否するが、発覚の恥辱をレイフより恐れ、虐待的な関係を続ける。愛と勘違いした虐待的な屈服に、関係は絶対的な堕落と悲劇へ向かう。イヴリンの末路は……
……社会反映と論争の含意についての文学的研究に膨らませず(確かに簡単だが、ここではしない)、この大胆で異端な映画の余波で視聴者が多層的に分断されるのは明らかだ。映画の設定時、公開時、現在の社会状況を考慮すると、どれだけ変わり、どれだけ変わっていないかがわかる。人種的混乱、社会的受容、恐怖、道徳の違いが時代で対立し、視点を狭め、すれ違い、再び分かれる。すべての側に偽善が残る——少なくとも大衆の複数の視点の一つだ。
……この映画を振り返ると、必然的に論争的で議論を求める質問が生まれ、今日の新聞見出しにも反映される。設定時、公開時、現在の観察から、レイフ(疑わしい性格)が白人だったら見方は変わるか? 用務員が白人ならイヴリンの恥辱は増減するか? エド(既婚で子供あり)の誘惑にオープンだったイヴリンが、レイフとの関係発覚を恐れるのは道徳的に偽善的か? 終盤の医師の「誰かを見つけるよう言ったが、そういう意味では……」は年齢か人種か? これは始まりにすぎず、別タイトル『ザ・シン』の多面的な定義を与える……
……アン・ヘイウッドのキャリア後期で最も挑発的な役の一つ(『ザ・フォックス』(1967)、『アイ・ウォント・ワット・アイ・ウォント』(1972)も異色)。苦悩するイヴリンの勇気ある演技は信じられ、共感できる。ジョン・ラファイエットも最小限だが支配的なレイフで変幻自在。ドナルド・プレザンスは精神科医として影響力ある誘惑を演じ、アール・ホリマンは運転手エドとして男らしさと魅力を。脇役にロニー・ブレイクリー、ドロシー・マローン、デイナ・エルカー、R.G.アームストロング、キャロリン・ジョーンズ。ロバート・ヴォーンは婦人科医として信頼感を与えつつ、微かな自己満足を。
……時折、明確にエクスプロイテーション的な作品が現れ、愉快的ではない。『グッド・ラック、ミス・ワイコフ』は愉しさを意図していない(悪いと言うのは不公平)。それでも容赦なく強力で魅力的。無視できず、忘れられない。真実は、たとえエクスプロイテーション的に描かれても、いつも美しいとは限らない。




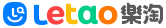













 好評 (295)
好評 (295)
 差評 (0)
差評 (0)