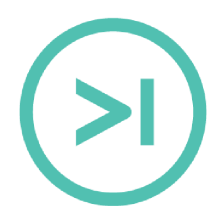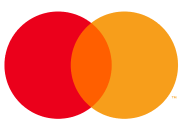1. 渇き
2026年2月8日、土曜日。大阪、心斎橋。
時刻は午後6時29分を回っていた。
Xiaomi 14 Ultraの冷たいレンズが捉えた世界は、残酷なほど鮮明だった。75mmの望遠レンズ越しに見る御堂筋は、インバウンドの熱気と、再開発で整然としすぎたビルの無機質な光に支配されている。
二階堂美咲は、スマートフォンの画面を指先で消し、ふう、と重い息を吐いた。
吐き出された白い息は、冬の寒さのせいだけではない。自身の内側に澱のように溜まった、鉛色の倦怠のせいだった。
今日、彼女は60歳になった。還暦である。
大手コンサルティングファー※請確認是否動物毛皮。動物毛皮製品屬於華盛頓條約条約牴觸物品,無法國際運送。ム「フェニックス・ストラテジー」の執行役員。年収は億を下らず、港区と芦屋にマンションを持ち、経済誌の「現代を切り拓く女性100人」に名を連ねる。
だが、今の美咲にあるのは、砂を噛むような乾燥した孤独だけだった。
「……キャンセルして正解だったわね」
部下たちが企画していたサプライズパーティーを、美咲は「急な体調不良」という嘘で当日にキャンセルした。
彼らの笑顔が怖いわけではない。彼らが向ける笑顔の裏にある、「接待」としての義務感を見るのが耐えられなかったのだ。かつて自分が上司に向けていた、あの空虚な眼差しを。
美咲は逃げるように会社を出て、気がつけば心斎橋の雑踏の中にいた。
目的もなく歩く足が、ふと止まる。順慶町(じゅんけいまち)。
かつて繊維問屋街として栄えたこの場所も、今は煌びやかなドラッグストアやホテルが並ぶ。だが、その喧騒から一歩引いた路地裏に、その店は静かに佇んでいた。
——ブランドクラブ。
知る人ぞ知る、高級宝飾とブランド品のセレクトショップだ。ここには、流行り廃りの激しい今のブランド品とは違う、時代を生き抜いた「本物」だけが集まる磁場のようなものがある。
重厚なガラス易碎品限空運,非易碎品可使用海運。 扉を押すと、カウベルの音と共に、微かな白檀と古い革の匂いが鼻孔をくすぐった。
「いらっしゃいませ。……おや、二階堂様ではありませんか」
店主の初老の男性が、磨き上げられたカウンターの奥から顔を上げた。彼は美咲の顔色を一瞥しただけで、余計な世間話を一切挟まず、ただ静かに会釈をした。こういう距離感が、今の美咲には心地よい。
「少し、強いものが見たいの。私の今の気分を、ねじ伏せてくれるような」
抽象的な注文だった。だが、店主は口元に微かな笑みを浮かべ、「少々お待ちください」と奥の金庫へ消えた。
数分後。
彼が持ってきたのは、黒いベルベットのトレイだった。その上に、たった一つ、指輪が置かれている。
美咲の視線が吸い寄せられた。
呼吸が、止まる。
「……赤」
ただの赤ではない。それは、深海の闇の中で何百年もの時をかけて凝縮された、生命の血そのものだった。
照明の光を吸い込み、内側からぬらりと発光しているような不気味なほどの艶。
「天然の血赤珊瑚(オックスブラッド)です。サイズは15.3ミリ」
「15ミリ……?」
美咲は眼鏡の位置を直し、思わず身を乗り出した。珊瑚において10ミリを超えれば大珠と呼ばれる世界で、15.3ミリという数字は異次元だ。
「しかも、見てください。この形。丸珠ではなく、わずかにドームを描くボタン系。それがこの石の『座り』を良くしています。まるで、惑星のようです」
店主がピンセットを使わず、白手袋をはめた手で恭しく指輪を差し出した。
美咲は震える手でそれを受け取る。
ずしり、とした重み。
8.24グラム。数値以上の質量を感じる。まるで、この指輪自体が意思を持って、美咲の掌に根を張ろうとしているかのような錯覚。
台座は現代の主流であるプラチナではない。K14WG——14金のホワイトゴールドだ。
昭和の中期からバブル期にかけて作られたと思われるその台座は、職人の手仕事による見事な透かし彫りが施されていた。
王冠のような爪(プロング)が、巨大な赤珊瑚を鷲掴みにしている。その姿は、獲物を捕らえて離さない猛禽類の爪のようでもあり、あるいは権力者が玉座を守るための剣のようでもあった。
「鑑別書はこちらに。ジェムリサーチジャパンのソーティングメモが付いております。『F4289』……これがこの子の管理番号です」
「F4289……」
美咲は呟きながら、その赤い球体を凝視した。
表面には一点の曇りもない。天井のダウンライトが映り込み、赤い宇宙に浮かぶ白い太陽のように輝いている。
17.29ミリという台座込みの直径は、指にはめれば関節を覆い隠すほどの威圧感があるだろう。
「サイズは8号です。ピンキーリングとしてお使いになるか、あるいはお直しも可能ですが……」
「いいえ」
美咲は遮った。
直感があった。これは、私の指輪だ。
8号。それはかつて、彼女がまだ若く、野心に燃えていた頃の薬指のサイズ。そして今は、少し節くれだった小指のサイズだ。
美咲は左手の小指に、その赤珊瑚を滑り込ませた。
金属の冷たさが肌に触れた瞬間、ドクン、と心臓が跳ねた。
指輪が脈打った気がした。
いや、気のせいではない。指の腹を通じて、珊瑚の奥底からドロリとした熱い何かが流れ込んでくる。それは活力であり、同時に強烈な「渇望」の味だった。
「これ、いただくわ」
美咲は即決した。価格などどうでもよかった。この赤を手放してはいけない。今の自分に欠けている「生への執着」が、この石には過剰なほどに詰まっている。
「ありがとうございます。……二階堂様、この石には不思議な言い伝えがありましてね」
会計を済ませ、包まれた指輪を受け取る際、店主が意味深な目を向けた。
「珊瑚は、持ち主の厄を吸うと言われています。ですが、これほど巨大なものになると、吸うだけでは飽き足らず、持ち主の運命そのものを書き換えてしまうことがあるとか」
「運命を書き換える?」
美咲は鼻で笑った。「今の私には、書き換えたい未来なんて残っていないわ。あるのは過去への後悔だけ」
「……過去もまた、運命の一部ですよ」
店を出ると、外は完全に夜になっていた。
冷たい風が吹き抜ける。だが、左手の小指だけがカッカと熱い。
美咲は我慢できず、路上で箱を開け、再び指輪をはめた。
Xiaomiのカメラを起動する。ISO200、1/102秒、f/1.8。
画面の中の赤珊瑚は、肉眼で見るよりもさらに鮮烈に、毒々しいまでの赤を放っていた。
「美しい……」
そう呟いた瞬間だった。
グニャリ。
視界の端から、風景が溶け出した。
最初は、めまいだと思った。徹夜続きの疲労が出たのかと。
だが、違う。
足元のコンクリートが波打ち、アスファルトが泥のように沈み込む感覚。
耳の奥で、キーンという高周波の音が鳴り響き、その直後、爆音のようなノイズが雪崩込んできた。
——ドンドコ、ドンドコ、ドンドコ。
腹に響くような、重低音のディスコビート。
——「おいコラ! どこ見て歩いとんねん!」
野太い大阪弁の怒号。
——排気ガスのむせ返るような臭いと、濃厚なタバコの煙、そして安っぽい香水の香り。
美咲は膝から崩れ落ちそうになり、とっさに近くの看板に手をついた。
その看板は、LEDの冷たい感触ではなく、熱を持ったネオン管の枠だった。
「うっ……」
強烈な吐き気に襲われ、美咲は目を閉じた。
世界が回転している。遠心分離機にかけられたように、今の記憶と、過去の記憶が混ざり合う。
60歳の知識、経験、狡猾さ。
24歳の情熱、無知、そして未練。
それらが赤珊瑚の指輪を媒介にして、強引に縫い合わされていく激痛。
「おい、ねえちゃん。大丈夫か?」
男の声がした。
美咲は荒い呼吸を整え、ゆっくりと目を開けた。
ぼやけた視界が、次第に焦点を結んでいく。
目の前に立っていたのは、見たこともないほど肩パッドの張った、紫色のダブルスーツを着た男だった。髪はジェルでテカテカに固められ、手には分厚いセカンドバッグ。
そして、男の背後に広がる景色に、美咲は絶句した。
心斎橋筋のアーケードではない。
そこは、毒々しいネオンの洪水だった。
原色の看板が、夜空を焦がすように明滅している。
行き交う人々は皆、何かに取り憑かれたように笑い、叫び、千円札の束を扇子のように振ってタクシーを止めていた。
シーマ。セドリック。クラウン。
角張った車体の列が、黒塗りの川となって御堂筋を埋め尽くしている。
美咲は震える手で、自分の顔を触った。
皺がない。
肌に、ピンと張り詰めた弾力がある。
視線を落とす。カシミヤのコートは消え、ボディラインを強調する真っ青なボディコンシャスなワンピースを纏っている。
そして左手。
あの巨大な赤珊瑚の指輪「F4289」は、小指ではなく、薬指に食い込むように嵌まっていた。
まるで、最初からそこにあるのが当然だと言わんばかりに。
美咲は近くのショーウィンドウ——そこには「ブティック・カメリア」というレトロなロゴがあった——に映る自分の姿を見た。
黒髪のワンレン。太い眉。意思の強そうな、しかしどこか不安げな瞳。
24歳。
二階堂美咲。
まだ何も持っていなかった頃の私。
「……戻った?」
声が震えた。だが、その声色は若く、張りがあった。
状況を整理しろ。美咲の中の「60歳のコンサルタント」としての人格が、即座に命令を下す。
夢ではない。この湿気、騒音、リアリティは夢の解像度を超えている。
タイムスリップ。
あり得ない事象だが、ビジネスにおいて重要なのは「なぜ起きたか」ではなく「どう対処するか」だ。
ふと、視界の端にある電光掲示板がニュースを流した。
『竹下内閣、支持率急落。リクルート事件の余波広がる』
『日経平均株価、3万4千円台を攻防』
1989年(平成元年)。
日本経済が狂乱の頂点へと駆け上がり、そして奈落へと突き落とされる直前の年。
美咲は掌を握りしめた。赤珊瑚の冷たい爪が皮膚に食い込む。
私は知っている。
これからこの国に何が起きるのか。
この街の不動産がどうなるのか。
そして何より——私が愛した男、桐島透が、どうやって破滅し、私の前から姿を消すのかを。
美咲の唇が、自然と笑みの形を作った。それは24歳の純朴な笑みではない。数多の修羅場をくぐり抜けてきた、魔女の笑みだった。
「面白いじゃない」
彼女は踵を返した。
向かう先は、順慶町ではない。
欲望の渦巻く街、宗右衛門町(そうえもんちょう)。
かつて自分がアルバイトをし、バブル崩壊と共に潰れ、借金を背負わされた伝説のクラブ「珊瑚礁」がある場所へ。
歴史を変えるのではない。
私が、歴史そのものになるのだ。
美咲が歩き出すと同時に、赤珊瑚の指輪が、ネオンの光を受けて血のように赤黒く瞬いた。
(第1章・前編 完 涙なしでは語れない感動の後編へ)





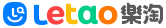










 好評 (74,176)
好評 (74,176)
 差評 (24)
差評 (24)